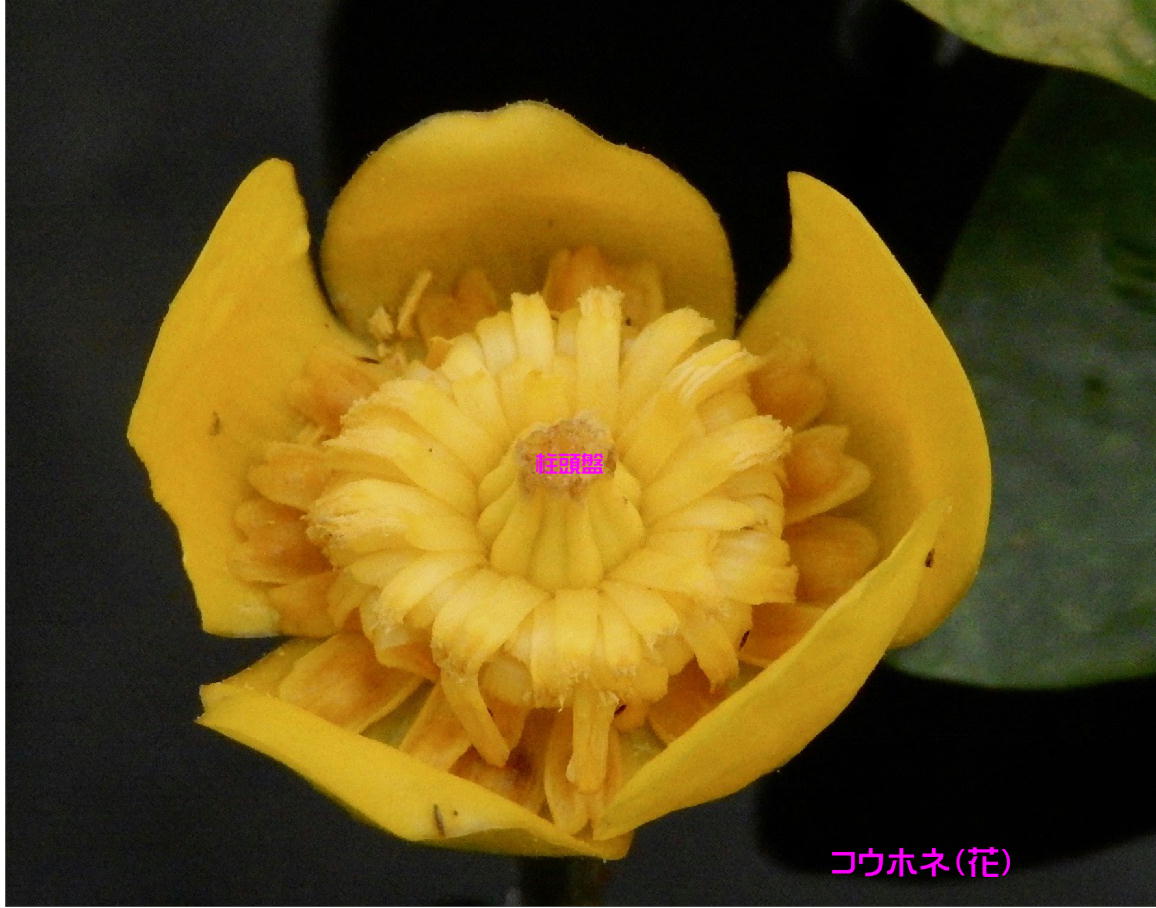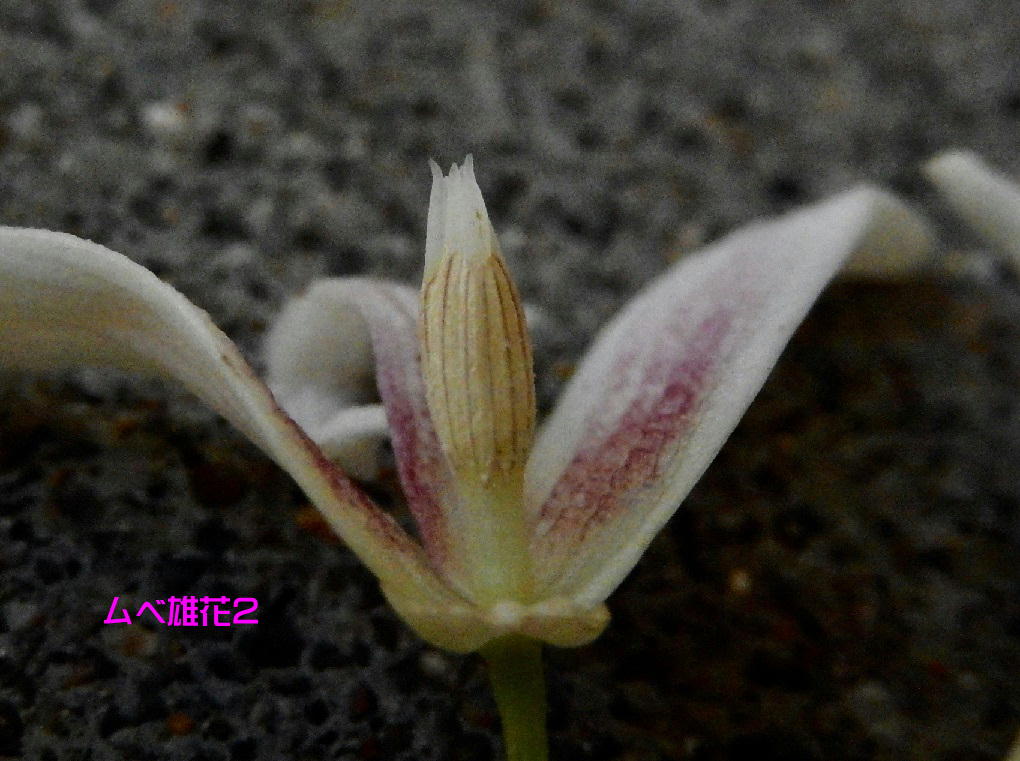ここは,「花」の普通や不思議を紹介するコーナーです。
F1 基本的な花の構造をもっている植物(両性花のみ)
まず,外側からがく・花びら・おしべ・めしべをすべての1つの花に備わっている植物の例をあげます。なお,合弁花・離弁花に植物を区分するのは,厳密な意味での系統分類では不適当であると言われています。また,単子葉植物には,合弁花・離弁花の区別はしないそうです。
○ 合弁花(花弁の基部が分離していないもの)
○ 離弁花(花弁が基部から分離しているもの)
めしべの数がゼロになることがある両性花
○ バラ科
めしべの数が複数ある両性花
○ マツブサ科シキミ属(旧シキミ科)
<メモ>
● シキミ
花の中央部分に8本のめしべが確認できます。
<参考>
めしべは被子植物の雌性生殖器ですが,その構成単位を心皮と呼びます。1つのめしべは1つの心皮からなる場合もあれば,複数の心皮が合体したものもあります。シキミでは,花の中心部に1つの心皮からなる構造が,規則正しく分離して8列あり,中央で接近しています。
○ バラ科
<メモ>
● ヒメバライチゴ
花の中央部分にあるけむくじゃらな構造がめしべの集団です。
○ ハス科
<メモ>
● ハス
花の土台部分(花托)が逆三角形にもりあがって,複数のめしべがその一部を外に出して中に埋もれる形になります。
<番外編>
○ スイレン科コウホネ属
<メモ>
● コウホネ
花の中心部に,複数の心皮が放射状に融合しためしべを形成します。先端部は平坦で柱頭盤と呼ばれます。一応,めしべは1本と数えられます。
F2 同じ株に雄花と雌花が形成されるもの(両性異花同株)
同じ株は基本的には同じ遺伝子をもっているはずですが,形成される花は雄花か雌花かどちらか一方です。これをABCモデルで説明するとどのようになりますか。
○ ウリ科
<メモ>
● キュウリ(キュウリ属)
上が雄花,下が雌花。単為生殖をするらしく,収穫には雄花はなくてもいいとのことです。
● ゴキヅル(ゴキヅル属)
雄花ではめしべは簡単には確認できませんが,雌花には退化したとされるおしべか見えます。
○ クルミ科
<メモ>
● オニグルミ(クルミ属)
風媒花。雌花の花序は上向きに立ち上がり,先端部は大きく広がっています。
○ アケビ科
<メモ>
● ムベ(アケビ属)
虫媒花。雌花は中央にめしべが3つあり,外側の基部に雄しべの痕跡の様な構造があります。雄花はおしべが6つあり,筒状に合着します。おしべの内側の基部にめしべの痕跡のような構造があります。
F3 雌株と雄株に分かれるもの(雌雄異株)
動物と同じように性が雄の個体と雌の個体とに分かれているもの。
○ ヤマノイモ科
<メモ>
● ヤマノイモ(ヤマノイモ属)
雄株と雌株があり,雌花の花序はぶらさがり,雄花の花序は上を向きます。